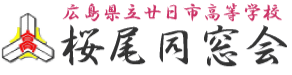寄稿 廿日市高等学校卒業後の研究と教育活動

S39卒 岩橋槇夫
理学博士
北里大学名誉教授
日本油化学会 フェロー
公益財団法人 コーセーコスメトロジー研究財団 理事
絵を描くことをはじめとして色々なことに興味があり、高校では美術部、文芸部、音楽部に所属した。人類初のソ連の人工衛星スプートニクの打ち上げや宇宙飛行士ガガーリンの言葉「地球は青かった」に触発され、小学生のころからロケットに興味を持ち、自作の望遠鏡で月や星を観測した。安いレンズを使っていたので色収差が大きく、月の周囲は虹色、スバル星団はきれいに色づき魅惑的であった。物理や化学が好きだった。高校3年の担任は助田忠三先生で、ある時先生に「私は将来何の職に向いているか」を問うと「教育職があっている」との答えがあった。また、数学の古川 清先生に先生のご出身の東京理科大学の受験を勧められ、第1回目の東京オリンピックが開催された1964年(昭和39年)に廿高を卒業し、東京理科大学 理学部化学科に入学した。
当時の私は、田舎から上京したばかりの喫茶店に入るのにも抵抗があるうぶな学生であった。新宿区の神楽坂にある理科大 理学部1号館の屋上にはお参りしないと落第するという通称「落第神社」がありむろん心からお参りした。当時の理科大は狭い敷地で校舎しか無かったが、近くに「佳作座」という映画館があり安い料金で多くの名作映画(アラビアのロレンス、ベンハー、ローマの休日など)を楽しんだ。校舎に通じる路地には多くの雀荘があり、2年生から麻雀を覚えた。賭け事は嫌いで賭けマージャンはしなかったが、麻雀の面白さにはまり込み2年の後期試験が通常通り1月初めに行われると3年への進級が危ぶまれるところであったが、60年安保の影響で理科大でも部活の部屋問題をきっかけとする学園紛争が起こり12月初めから学校は封鎖され期末試験は3月に延期された。延期が分かると直ぐに教科書とノートを抱えて広島に戻り、ひたすら勉強、おかげで無事に3年に進級できた。
理科大の講義は厳しく、しっかり勉強させられた。3年次の高分子化学、コロイド化学、量子化学は4年生進級の必須科目で、特に量子化学は定期試験ではなく隔週ごとの日曜日の午後1時から試験があった。先生の授業は難解で、何が何だか分からず、どんな問題が出るのか皆目見当もつかなかった。「出来が悪ければ1回だけは追試する」と言われた先生の言葉を信じ、毎回、試験後は黒板に書かれた問題を写し、夕方まで麻雀をしたあと友人の下宿に十数冊の参考書を持ち込み、皆で勉強、問題を解き、翌々週の追試でやっと合格という日々だった。今思えば先生は休日を返上され、講義の時間を試験で無駄に使うことなく、また、試験範囲を限ることで学生が自主的に勉強するように仕向けられていたようである。
日本のコロイド・界面化学を牽引されていた目黒謙次郎先生の授業は冗談が多く面白かったが、いざ試験を受けると冗談しか覚えていないことが判明。追試を2回受けた。さすがに3回も勉強するとコロイド・界面化学が好きになり、4年の卒業研究ではコロイド・界面化学を研究しようと思ったが、目黒研究室のドアに「コロイド化学の成績が悪い人お断り」の張り紙があり、断念。第二希望の無機錯体化学の関根達也先生の研究室で「ラジオトレーサー法によるBaおよびRaの硫酸およびシユウ酸錯体の安定度定数の研究」を行った。4年次には教員免許習得のため教育実習を母校 廿日市高等学校でお世話になった。高校を卒業してからそれほど時を経ていなかったので、私をよく覚えておられる化学や物理の先生方がおられ、懐かしく、また、色々なことを任され、大変お世話になった。
姉が結婚した時、義理の兄が広島大の博士課程の学生だったこともあり義兄への憧れからか中学のときから自分も大学院に行くことに決めていた。そして、学部では諦めた「コロイド・界面化学」を研究したく、東京都立大学理学研究科の佐々木恒孝先生の研究室を受験した。面接のとき佐々木先生から君は何を研究したいのかと問われ、「ラジオトレーサー法を使う研究がしたい」の一言がそれからの人生を決定したようである。
佐々木研では新進気鋭の当時助手であった田嶋和夫先生(現 神奈川大学特別招聘教授)の指導の下、「トリチウム標識非イオン性界面活性剤の合成と気液界面吸着量の測定」というテーマで研究した。田嶋先生はエネルギッシュで、研究の楽しさ、面白さ、さらにお酒の飲み方を教えていただいた。修士の2年間の研究だけで3報の欧文論文を出し、研究者としてまずまずのスタートになった。修士修了後そのまま研究室の助手になり、アメリカから帰られたばかりの助教授の村松三男先生の指導の下、主に「ラジオトレーサー法を用いた水面上不溶性単分子膜の研究」を行った。村松先生には研究の進め方、英語論文の書き方を徹底してご指導いただき、上に立つ者の行動とあり方、歴史の見方、社会人として必要なことを様々教えていただいた。おかげで研究が進み、論文も自分で書けるようになった。29歳の時、これまでの論文をまとめ、理学博士の称号を東京都立大学からいただいた。
33歳の時、村松先生と「溶液と溶解度」の著書で世界的に著名な横浜国大の篠田耕三先生の紹介で家内と小学校1年の長男と幼稚園の長女を連れ、1年半(1979-1981)アメリカ合衆国ニューヨーク州のクラークソン大学のB. A. Pechica先生(英国人で90歳を超える現在もプリストン大学教授)のもとで博士研究員として、「非常に低い表面圧力測定」と「水面上の脂肪酸結晶の示す平衡拡張圧力の結晶サイズの効果」の研究を行った。そこでは、上に立つ人ほど良く働くことやその考え方や仕事ぶりをしっかりと勉強した。英国人の「日本の古武士に似たやせ我慢」をしばしば拝見した。また、先生からそれまで曖昧だった「熱力学の適応範囲、現実に使える熱力学とは何か」を体得させていただいた。
帰国後、私がトリチウムと単分子膜を扱えることを知った東大原子核研究所から頼まれ「トリチウム標識脂肪酸のLB膜を使ったニュートリノの質量測定」を東大、東北大、東工大などの先生方と共同で行うことになった。トリチウムから出るベータ線のスペクトルを原子核研究所にあるスペクトルメータで正確に測定するとニュートリノの質量を算出できる。ビッグバーン以来宇宙は膨張を続けているが、宇宙を構成する素粒子のニュートリノがある程度の質量を持てば宇宙は収縮するとの予想であった。しかし、我々の研究で質量の上限は明らかになったが、下限は不明であった。同時期に東大の小柴昌俊先生が超新星爆発の際のニュートリノの観測に成功し、2002年にノーベル物理学賞を受賞された。
北里大学へ移られていた村松三男先生の招きで1985年9月(39歳)に北里大学 衛生学部 化学科の講師として着任した。ただ当時は研究室も実験装置も全くない状態で、これまでの研究を継続することはできなかった。何かしなくてはと学生実習室にあったオストワルド粘度計で鎖長を変えた直鎖アルコールの粘度を測定、自作の装置で密度を測定、さらに東京都立大の加藤 直先生(現 都立大名誉教授)が岡崎の分子科学研究所にNMRでの自己拡散係数測定に行かれるとき、先生のマシンタイム中にアルコールの自己拡散定数を測定していただいた。種々データを組み合わせることでアルコール液体中の分子の動的挙動を明らかにし、着任後1年半で北里大での最初の論文を出すことができた。「素晴らしい仲間さえいれば何もなくとも研究できる」という自信がついた。
その後、「チョコレートの科学」や「脂質の結晶構造の研究」の世界的権威である広島大学の佐藤清隆先生(現 広島大名誉教授)の依頼もあり、「脂肪酸など脂質の液体構造」を以後のテーマにした。結晶構造はきれいな結晶さえ作れれば少ない試料でも研究は可能であるが、液体構造の研究には高純度試料が大量に必要である。学会で友人になった企業の方から充分な量の試料を共同研究として提供していただいた。脂質の液体構造は一つの測定法だけでは真の姿を知ることは難しい。密度、粘度、自己拡散係数、ESR、NMR、近赤外分光、X線回析、中性子散乱など様々な結果を組み合わせることで初めて全容が明らかになる。これら実験上の困難から脂質の液体構造の研究は世界的にほとんど行われていない。最近になって環境やエネルギー問題の観点から脂肪酸のメチルエステルなどの液体構造が報告され始めている。今までに上梓した本は熱力学やコロイド・界面化学の教科書、油脂や界面化学の技術者・研究者向けを合わせて26冊になった。
北里大では助教授を経て1994年に教授、学部編成により理学部化学科「分子構造学講座」の教授となり、研究室から438名の学生を世に送り出し卒業生は色々な分野で活躍されている。2011年3月に65歳で定年退職後、引き続き非常勤講師として72歳まで「界面化学」を教えた。同じく2011年から10年間 東京理科大 理工学部(野田)の機械科の学生に「化学」を、2012年から4年間 理学部(神楽坂)化学科の学生に「光化学」を教えた。付け加えになるが、都立大の助手の時には千葉大と武蔵工業大で「化学」を教え、北里大教授の時は信州大、そして都立大の理学研究科や工学研究科で「脂質化学」や「界面化学」を講義した。また、学会で知り合った企業の方から頼まれ、72歳から6年間、コーセー美容専門学校の校長を務めた。美容の世界は研究の世界と全く異なっていたが、興味深く、高校時代に培った美術のセンスが役立った。
これまで多くの大学や専門学校の学生を指導したが、学生の本質はどこも変わりがない。かくして、研究者として、また、廿高時代の助田先生の言葉通り教育者の道をたどることになった。これまでやって来られたのは多くの素晴らしい先生方、友人に恵まれたおかげである。